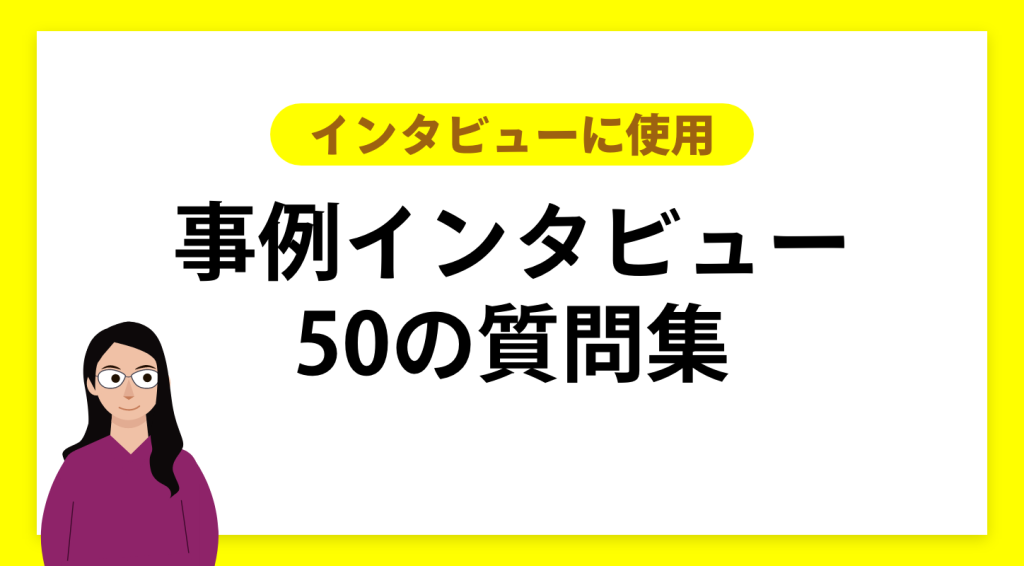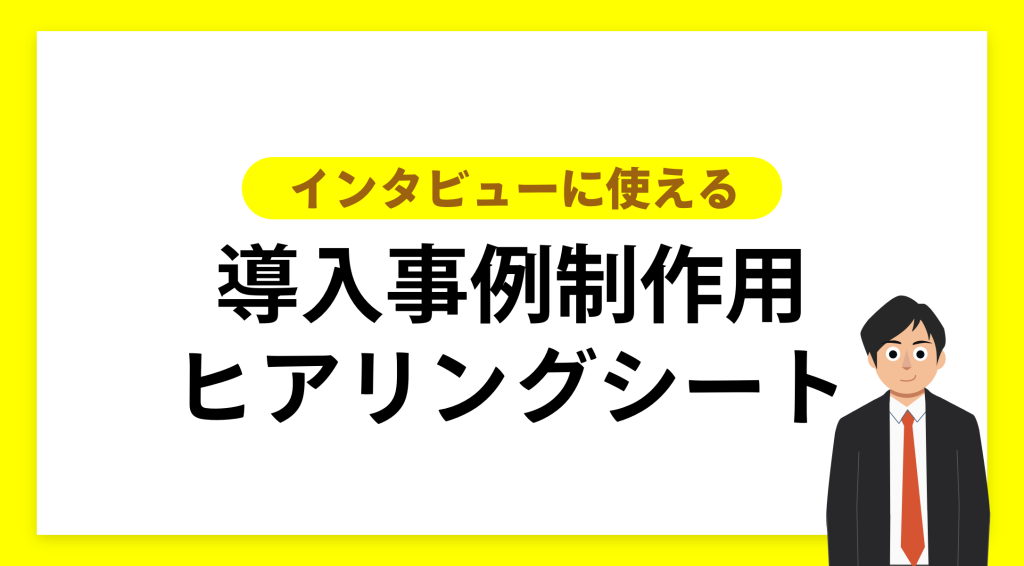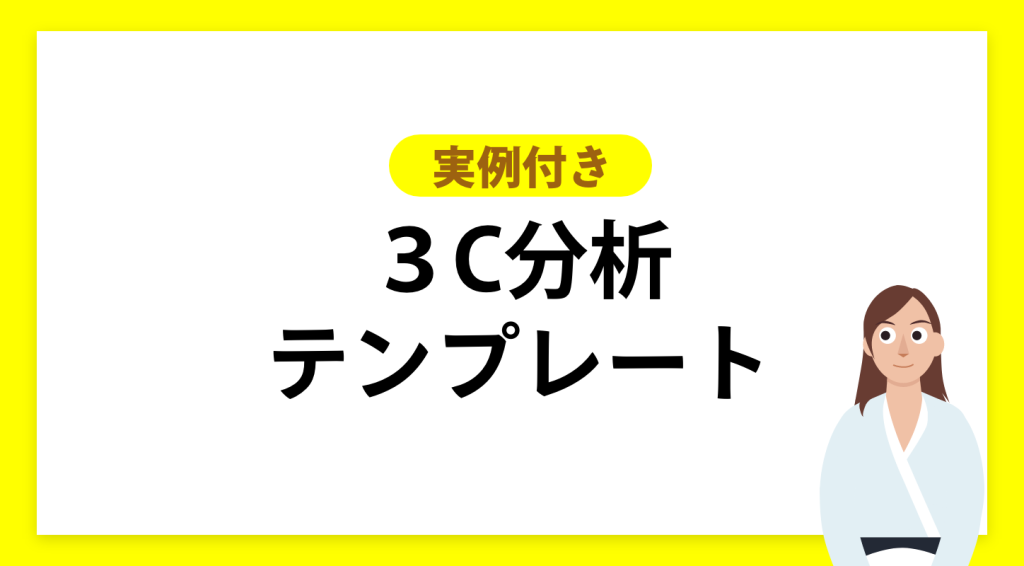動画を活用したプロモーションやブランド認知が活発化している中で、導入事例動画・インタビュー動画によってプロダクトの魅力を伝えるという手法も広がりを見せています。テキストコンテンツとは違った効果を期待できるものの、クリエイティブ面では動画ならではの難しさがあるのも実際のところです。ここでは、導入事例動画・インタビュー動画の活用方法や制作方法、クリエイティブのポイントまで紹介します。
シーラベルでは、「導入事例記事・動画制作」にお困りの企業様を支援しています。
⇒導入事例記事・動画制作 サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
導入事例動画を作るメリットとは

スマホやタブレットの普及、通信回線の高速化を背景に、BtoBマーケティング手法の一つとして定着しつつある動画コンテンツ。導入事例動画は、ユーザーの実際の声を届けられることから、CVR向上に役立つとして期待が高まっています。
現在は、インタビュー動画をはじめ、CGやアニメーションを利用したもの、ドキュメンタリータッチなど、クリエイティブにおいても様々な工夫が取り入れられています。まずは、導入事例動画を制作するメリットを見ていきましょう。
共感を得やすい
動画は音と映像による訴求力を持つため、テキストコンテンツよりも短時間で鮮明なイメージを植え付けることができ、共感を醸成しやすいというメリットがあります。クリエイティブを工夫することで、製品・サービスの機能性やメリットを直感的に理解してもらうこともできるため、ソリューションに対する説得力が生まれるという効果が期待できます。
短時間で多くの情報を伝えられる
テキストコンテンツの場合、製品・サービスのメリットや機能を説明しようと思うと、どうしても文字数が多くなりがちです。導入事例動画であれば、映像と音声を利用して短時間で多くの情報を伝えることができます。
また、実際に利用している様子を動画にすれば、操作性の良さや簡便性を訴求することもできます。短時間でプロダクトへの理解を深められる点は、テキストコンテンツにはないメリットといえるでしょう。
拡散を狙える
導入事例動画は、自社のWebサイトやメルマガだけでなく、YouTubeやInstagramといったSNSでの展開も可能です。視聴者が面白いと感じれば、拡散してもらえる可能性があるため、より高いプロモーション効果を生むことがあります。
導入事例動画の活用場面

導入事例動画を制作すると、様々なチャネルに活用できます。どのようなシーンで役立つのかを見ていきましょう。
動画配信プラットフォーム・SNS
制作した導入事例動画を多くの人に見てもらいたい場合に役立つのが、動画配信プラットフォームやSNSです。YouTubeやFacebook、Instagram、Twitterなどを活用すれば、これまで接点を持てなかったユーザーへの認知度向上やリード獲得の施策として活用できます。
自社のWebサイト・メルマガ
自社のHPはもちろん、ランディングページやメルマガでも動画を活用できます。導入事例動画は、プロダクトやサービスを導入するか検討しているユーザーの背中を押す役割を果たすため、CVR向上に大いに役立ちます。
営業現場
商談の際に、導入事例動画を視聴してもらうという使い方もできます。資料を読んでもらうよりも短時間でメリットを理解してもらえ、かつ営業担当のスキル格差によらず、説得力のある商談を展開できるというメリットがあります。とくに、オンライン商談との親和性は高いといえるでしょう。
ある程度の本数をストックしておけば、顧客の課題に合わせた動画を視聴してもらうこともでき、有効な営業ツールとなります。
イベント
説明会や展示会、ウェビナーなどに導入事例動画を活用することも可能です。インタビュー動画は第三者の目線から導入のメリットが語られるので、大勢が集まる場所で説得力ある情報を発信したい場合にも効力を発揮します。
短時間で要点を伝えられるほか、タイムテーブルが決まっているイベントでも容易に組み込めるというメリットもあります。
導入事例動画の制作方法5ステップ

ここでは、実際に導入事例動画を制作する際の流れを6つのステップに分けて説明します。
ステップ1:目指すゴールとコンセプトを決める
まずは、導入事例動画により何を実現するのか、ゴールを明確にします。活用場面や期待する効果を明確にすることで、どのような動画を制作すべきなのか、方向性が見えてきます。
続いて、動画のコンセプトを決め、制作を進めるときに目線がブレないようにします。コンセプトを決めるときは、「誰に・何を・どのように」の観点から、一つずつ明確にしていくと進めやすいでしょう。
●誰に伝えるのか
ターゲット像を明確にして、動画のスタイルやデザイン性、訴求ポイントを決めます。
●何を伝えるのか
自社の製品・サービスの、どの部分にフォーカスするのかを決めます。
●どのように伝えるのか
インタビュー形式の導入事例動画の場合、導入先企業に登場してもらうことになります。経営者や幹部クラスに登場してもらうのか、導入を決めた担当者または実際に利用している現場の社員に登場してもらうのかを決める必要があります。
動画のターゲットと伝える内容に応じて、有効な方法を検討しましょう。
ステップ2:予算を決める
導入事例動画の制作方法は、外部の制作会社に発注する方法、または自社で制作する方法のいずれかを選択します。外注するメリットは、クオリティを担保しやすいことや社内リソースを割かずに済むという点が挙げられます。自社制作のメリットは、コストを抑えられることです。
現在は、動画の制作・編集が簡単にできるソフトウェアも提供されているので、自社で制作するハードルは下がっています。ただし、クオリティ面では、やはりプロのレベルに追いつくのは難しいといえます。双方のメリット・デメリットを踏まえ、自社の予算や目的に応じて選択するとよいでしょう。
外部に発注する場合の制作費の項目を以下に挙げます。
- 企画・構成
- シナリオ・コンテ
- 撮影(スタッフ人数、使用機材による)
- 編集
- ナレーション
- BGM
- 素材購入費
- イラスト・アニメーション・CG
動画制作会社によって、全工程を内製化したりテンプレートを用意したりして低コストを実現しているケースもあれば、コストはかかるもののインパクトのあるクリエイティビティにこだわる制作会社もあります。自社が何を優先したいのかを明確にしたうえで選択することが失敗を防ぐポイントです。
ステップ3:構成・シナリオを決める
次は、構成とシナリオを具体的にするステップです。導入事例動画に盛り込む基本的な要素としては、以下のものがあります。
- 導入先企業の事業内容・登場人物の紹介
- 導入前に抱えていた課題
- 課題を解決した製品・サービスの紹介
- その製品・サービスを選んだ経緯や理由
- 製品・サービスのソリューションによる効果・メリット
- 導入事例のまとめ
以上の要素を取り入れてシナリオを作成すれば、導入事例動画としてのストーリーが整います。どの要素にフォーカスするか、どのように強調するかによって、時間配分や動画のスタイルを調整するとまとめやすくなります。
ステップ4:撮影に必要な準備を整える
シナリオに沿って、必要なものを撮影するための準備を整えます。当日の撮影をスムーズに進めるには、以下の調整や許可が必要です。
- 撮影場所の使用許可(使用時間についても調整)
- 撮影機材の搬入許可
- 撮影機材の置き場所を確保
- 撮影スタッフが出入りするための許可
また、撮影場所として適しているかどうかも事前に確認しておきます。
ステップ5:撮影・編集
シナリオに沿って撮影し、終了したら編集作業に入ります。編集作業は以下の流れで進めていきます。
- 音声を書き起こして、使用する部分とカットする部分を確認する
- 要素をつなぎ合わせた粗編集版を制作して、大まかな構成と尺を確認する
- 構成に合わせたナレーション原稿を作成する
- 音声やテロップなど細かな要素も入れたプレビュー版を制作する
- ナレーションを収録する
- BGMを挿入する
- 最終調整
登場してくれた導入企業にも内容を確認してもらう場合は、修正を反映しやすいタイミングで見てもらうようにするなどの考慮が必要です。最終調整の段階で大幅に修正することになると、手間もコストも余分にかかってしまうため注意しましょう。
効果的な導入事例動画を作るポイントとは

効果的な導入事例動画に仕上げるには、制作時に留意すべきポイントがいくつかあります。一つずつ見ていきましょう。
説得力を生み出す構成
導入事例動画で重要なのは、いかにして説得力を高め、視聴者の納得感を醸成するかという点です。そこで重要となるのが、視聴者となる検討企業の視点を強く意識することです。わかっているつもりでも、制作中には自社が伝えたい情報を優先したくなる心理が働きやすいものです。検討企業の便益にフォーカスした構成となっているかを常に確認しながら進めていくことは、重要なポイントです。
利用シーンを見せてイメージ醸成
導入事例動画ならではのメリットが、実際に自社の製品・サービスを利用しているシーンを見せられること。プロダクトへの理解促進もできるため、うまく取り入れるとよいでしょう。目に見えないサービスの導入事例の場合は、イラストやアニメーションを使うなどの工夫をすると理解を深めやすくなります。
視覚的なわかりやすさ
インタビュイーの話の内容は、音声だけでなく視覚的にもわかりやすくする工夫をすることがポイントです。たとえば、構造を図解で表示したり、テロップやアニメーションを挿入したりすることで、すんなり理解が進みます。また、映像のつなぎ部分にはインサート映像をうまく利用するなど、変化をつけたり強調したりするのも視聴者を飽きさせない良い方法です。
インタビュイーの見せ方を工夫する
インタビュー動画の場合、インタビュイーをどのように撮影するかという点も押さえておきたいポイントとなります。
インタビュイーがカメラ目線で話し続けると、視聴者が圧迫感を持ってしまうため、目線をずらした角度となる構図でセッティングするとよいでしょう。また、できるだけ自然体で話している様子が撮れるよう、リラックスした雰囲気を作るなどの工夫も必要です。
適切な尺
導入事例動画の場合、長すぎると視聴者の集中力が途切れてしまうので、一般には長くても5分程度が多くなっています。
ただし、動画を活用する場所やターゲットによって適切な尺は変わります。たとえば、ターゲットとなる見込み客の関心度が低いことが想定される場合は、途中離脱されないよう、短く端的に伝えたり飽きさせないような工夫をしたりするとよいでしょう。
再生する場所によっても、じっくり伝えたほうが効果的なのか、2~3分程度にまとめたほうが目的を果たしやすいのかが変わるため、事前にしっかり検討しておくことが重要です。
ユーザーの生の声を届ける導入事例動画をうまく活用しよう
動画コンテンツを活用したマーケティングは、すでにスタンダードな手法として定着しつつあります。動画制作会社にくわえ、自前で制作・編集できるソフトも数多く提供されており、選択の幅が広がっていることもこれを後押ししているといえるでしょう。
製品・サービスの魅力やメリットをユーザーの生の声で表現できるのが、導入事例動画の大きなメリットです。CVRの向上やCPAの削減に高い効果を期待できるほか、工夫次第では自社のファン獲得につながります。テキストコンテンツでは表現しにくい内容を伝える手段として、検討してみてはいかがでしょうか。
DX事例プラットフォーム「シーラベル」を運営する株式会社シーラベルでは、導入事例動画の制作・活用支援サービスも展開中です。
⇒導入事例記事・動画制作 サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
導入事例動画をマーケティングに活かしたいという場合は、ぜひお気軽にお問い合わせくだい。